製造業がWEBマーケティングで使える補助金、助成金
- 公開日|
- 2025.08.08
- 最終更新日|
- 2025.08.08
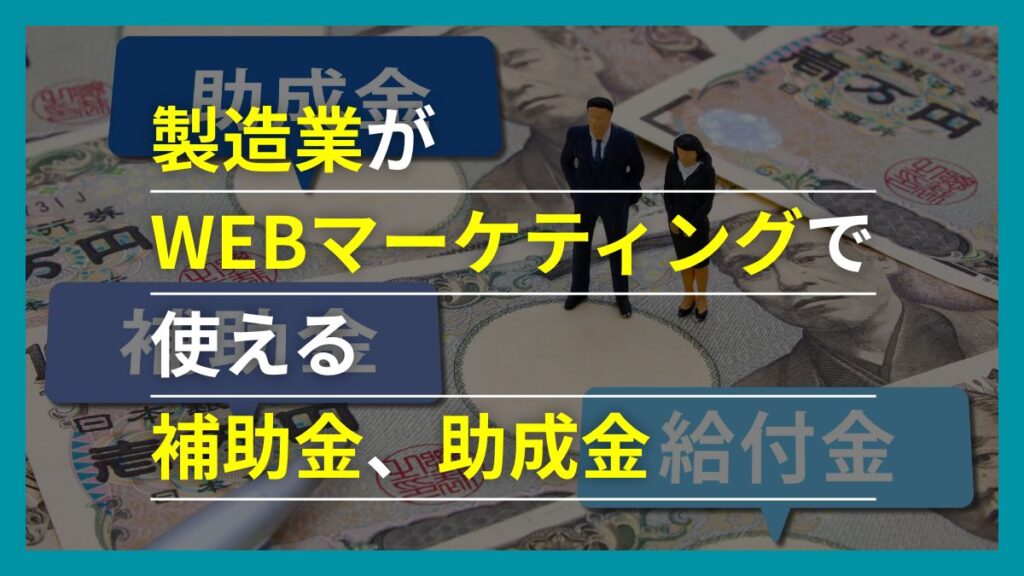
製造業にとって、WEBマーケティングは販路拡大・新規顧客獲得の強力な手段です。しかし、ホームページの新規制作やSEO対策、広告出稿、ツール導入には相応のコストがかかるため、二の足を踏む企業も少なくありません。
そこで注目されているのが、国や自治体が提供する補助金・助成金制度です。うまく活用すれば、WEBマーケティングへの初期投資を抑えつつ、競争力強化につなげることが可能です。以下では、製造業がWEBマーケティングで活用できる主な制度と活用ポイントを紹介します。
目次
1. 小規模事業者持続化補助金(一般型)
概要
日本商工会議所が主導する補助金制度で、小規模事業者が販路開拓や業務効率化を目的とする取り組みに対して補助を行うものです。WEBマーケティング関連の費用も対象となります。
対象となる取組例
- ホームページの新規作成・リニューアル
- 自社製品のPR用コンテンツ(動画・LP等)の制作
- Google広告やSNS広告の運用費
- メールマーケティングやSEO対策の外注費
補助率・上限額
補助率:2/3(残り1/3は自己負担)
上限額:50万円(※条件により100万円に拡大する場合あり)
活用ポイント
経営計画書と補助事業計画書の提出が必要です。商工会議所・商工会がサポートしてくれるため、事前相談を活用するのが成功の鍵です。
2. IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)
概要
中小企業のIT活用を支援する制度で、クラウドツールや業務改善アプリケーションの導入費用などが補助されます。WEBマーケティングに必要なツール導入も該当します。
対象となるツール・費用
- マーケティングオートメーション(MA)ツール
- 顧客管理システム(CRM)
- WEB広告運用プラットフォーム
- ECサイト構築システム
- LP制作機能を備えたCMS
補助率・上限額
補助率:1/2〜2/3(ITツールの区分により変動)
補助額:最大450万円(通常枠は最大350万円)
活用ポイント
導入希望のツールが「IT導入支援事業者」に登録されている必要があります。ツールの選定と申請手続きは支援事業者が代行してくれるため、負担は少なめです。
3. ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
概要
新製品・サービスの開発や業務改善を支援する制度。製造業にとっては生産プロセスの見直しや販路開拓戦略の一環として、WEBマーケティングを絡めた申請が可能です。
対象となる取り組みの例
- 自社新製品のPR専用WEBサイトの構築
- 海外向け販路開拓を見据えた多言語サイトの構築
- デジタル広告を活用した商材テストマーケティング
- オンライン展示会への出展とコンテンツ制作
補助率・上限額
補助率:1/2(小規模事業者は最大2/3)
補助上限額:最大1,250万円(枠によって異なる)
活用ポイント
ものづくり補助金は競争率が高いため、「革新性」と「収益性」を明確にした事業計画が必要です。専門家(中小企業診断士など)の協力を得るのがベストです。
4. 地方自治体の独自支援制度
概要
都道府県や市区町村単位で独自に設けている補助金・助成金制度にも、WEBマーケティングに使えるものがあります。内容や上限額は地域ごとに異なるため、こまめな情報収集が不可欠です。
主な支援内容(例)
- 展示会出展費用の補助(オンラインも含む)
- 中小企業向けWEB販促支援事業
- デジタル技術導入支援(広告・SEO・動画制作など)
活用方法
「〇〇市 WEBマーケティング 補助金」などのキーワードで検索したり、地元の商工会議所・産業振興課に直接問い合わせると確実です。
5. 活用時の注意点と成功のポイント
①公募スケジュールの把握
補助金は年に数回しか募集が行われない場合もあります。定期的な情報収集が必要です。特に小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金は応募期間が限られるため注意しましょう。
②実績報告が必要
補助金を受けた場合、事業終了後には「実績報告書」や「経費証明書類」を提出しなければなりません。不備があると補助金が支給されないケースもあるため、証拠書類はしっかり保管しておきましょう。
③専門家の力を借りる
申請書作成や戦略立案に不安がある場合は、行政書士、中小企業診断士、商工会議所などの専門家のアドバイスを受けましょう。補助金の採択率向上にもつながります。
まとめ
製造業におけるWEBマーケティングは、単なる情報発信にとどまらず、「受注につながる戦略的活動」として重要性が高まっています。補助金や助成金を活用することで、限られた予算内でも効果的な施策を実行できます。
まずは、自社にとって最適な制度がどれかを見極め、必要な計画書や見積書の準備を始めましょう。情報収集と準備を怠らなければ、資金的ハードルを下げながら、持続的な売上拡大を図ることが可能になります。







